シンオウ徒然道中記・1
トラブル・トラブル
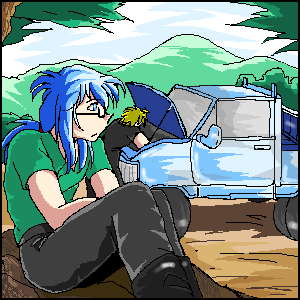
車が一度ガクンッと前につんのめって止まった。反動で、車内にいた男二人は背中をしたたかにシートに打ちつけた。
近いうちに来るとは分かっていた衝撃。心の準備は出来ていたのに、実際に来てみると体も反射神経も無防備だった事を思い知る。
「はふっ」
運転席のブソンが、天井を仰いで大きく息を吐く。
「なんとか騙し騙し山越えするつもりだったが、やっぱダメだったな。しかし、こんなに早くエンストするとは思わなかった…」
「……だから、遠回りでもふもとに出た方がいいと言ったんです」
かすかに頬を膨らませ、助手席のバショウが不機嫌な声でつぶやいた。
バショウとブソンは、秘密結社ロケット団特務工作部に所属する工作員である。
任務のためにシンオウ地方に来ていた二人は、無事仕事を終わらせ、このまま車で山を越え港に出る予定だった。
カントー、ジョウトに拠点を置くロケット団は、北の大地シンオウには存在していない。今なら、なんの痕跡も残さずにこの地を離れる事が可能なのだ。
それなのに。
「エンジンの不調が分かっていながら山に入るなんて、自殺行為ですよ」
「ふもと回りは倍以上の時間がかかる。警察をまくには危険だと思うだろう」
「こんな山の中で立ち往生では、結局同じ事じゃありませんか」
伊達メガネの奥で、冷たいバショウの目が細くすぼまったまま相棒を見据える。
少なくとも、バショウはこの車での山越えには反対していた。彼は石橋を叩いて渡る性格だ。不安要素を極力省いた堅実な作戦を好む。
しかし、ブソンは真逆に位置する性格だった。ある程度危険な橋でも渡ってしまえばそれでいいという、「結果オーライ」な男なのである。
「とにかく、出来るところまではやってみるさ」
大柄な金髪男は車を降りるとボンネットを開け、そのガタイのよい上半身を突っ込んだ。
ブソンは、バショウが機械類に触れる事をひどく嫌う。バショウはいわゆる「機械オンチ」だった。
操作は出来るが修理が出来ない。それどころか、修理のつもりで壊した機器は数知れず。だから、今回もブソンが手伝いを望んでいない事は分かりきっていた。
車から離れ、エンジンルームに頭を入れるブソンの姿を眺めやる。まるで車に食われているみたいだ、と思った。
食われている…といえば。
「お腹がすきましたね…」
ため息混じりで、思いついたままの言葉を口にする。
任務に集中していたため、食事やそれに準ずる行為をすっかり忘れていた。食べたのはいつだろう。今はもう昼すぎだが、何かを口にしたのは空が暗かった頃と記憶している。
その時、ブソンが大声で言った。
「こりゃぁダメだ! 車は置いていくしかねぇ! 街まで歩くぞ、バショウ!」
街まで歩く? ここは峠で、しかも街までは相当に離れた山道だ。人目を避けるためにわざわざ選んだ逃げ道が、まさにあだになった。
急いでいるこの状況で歩いて下りようなんて、一体何時間を無駄に費やすつもりなんだ。
とはいえ、他に方法はない。
腹の底から長い息を吐き、バショウは鉛を飲み込んだような気分でのろのろと立ち上がった。